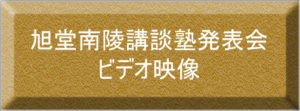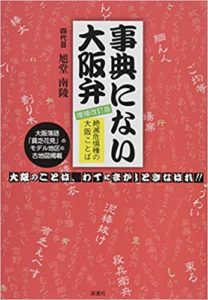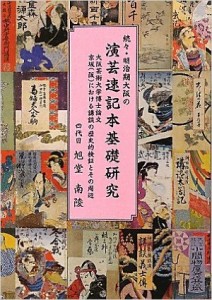明治の初期までは日本の話芸は、僧侶の説教、講談師の軍談を中心とする講談(古い言い方では講釈)、落語家の演じる落語(古い言い方では落し噺)が中心でした。そして講談と落語は僧侶の説教話芸から派生したものです。 平安時代も末頃になると公郷相手のエリート仏教では教線の拡大につながらない、庶民を相手に仏の教えをやさしく説くことが必要だという考えが天台系の仏教から興ってくる。
庶民相手にどうすれば仏の教えを、理屈っぽくなく説くことができるのか。考えだされた方法は、言葉のしゃれやこっけいな話をとり入れる方法。これはやがて落語へと発展していく。もう一つは僧侶自身が加わったり見聞した合戦の様子を伝えて知的好奇心をあおる方法。ひらたく言えば、やじ馬根性を刺激して、仏の教えに結びつけていく方法。これは軍記説教から軍談へと発展していく。
説教の技法としては節をつけて説教をする節談説教、絵を用いて説教する絵説き説教がある。その中間の形として節をつけて絵説きをする説教もある。
節をつけてしゃべることは、心地よいリズム感を伴うため、聞く者を魅了した。
この節付けはやがて明治に興った浪花節、さらには歌謡曲、俗に演歌艶歌といわれる日本の歌の独自の技法、こぶし、ゆり、もどし等の歌い方へと流れていく。
絵説き説教は、地獄、極楽、鬼、釈尊、あらゆる仏教にかかわる人物や事象を具体的なイメージを伴って庶民の前に現出させた。紙芝居と同様、文字の読めない庶民にとっては楽しい娯楽であった。
しかし、明治時代に入り、このような芸能の形を装っての布教活動は邪道であるという考えが、東西本願寺、すなわち浄土真宗の中でおきてきた。ついに説教話芸による布教は禁止され、北陸地方を中心に細々と伝承されるだけになった。
近年は説教話芸の見直しの動きが出て、若い後継者も育っている。
この説教話芸の影響は、今日の寄席芸にも色濃く残っている。前座という用語は説教のお前座修行からであるし、同様に高座という語も説教由来の言葉である。
大阪の講談も落語も小拍子という小さな拍子木を使うが、これも柝(たく)と称する仏教由来のパーカッション楽器にほかならない。
比叡山の天台宗こそが説教話芸の源流に位置し、説教話芸の二大流派を生んでいる。二大流派が生まれるまでは徐々に技法が進化してきたことだろう。
二大流派とは、平安末期から鎌倉時代にかけて、説教話芸の大家と言われた澄憲(ちょうけん 一一二六~一二〇三年)と息子の聖覚(一一六七~一二三五年)によって確立された三井寺派である。彼は生没年不詳であるが寛元年間(一二三四~一二四六年)頃に三井寺派を創始したと考えられている。又、聖覚は後に天台から浄土門に移った人物で、これで天台から浄土系への説教の技法の流れがわかる。
僧侶は平和を説くかたわら、寺領を守るために武家集団と戦った戦闘員であり宗門は戦闘団体である。家康の一向一揆鎮圧までその戦闘集団としての歴史は長い。
『源平盛衰記』『太平記』は文学作品というより、説教のテキストである。『源平盛衰記』や『太平記』には、澄憲そのものも登場するが、天台の僧侶が登場するのは、自宗の僧侶を物語の中で多く登場させて布教の効果を高めることを狙ったことも一因であろう。
軍記説教から軍談へ
『源平盛衰記』(平家物語)や『太平記』に異本が多いのは、形を整えなかった頃から、説教僧は自分の参加した合戦や仲間の説教僧と情報を交換したりして、オリジナルのテキストを作っていたからであろう。織田信長と石山本願寺の合戦も『石山軍記説教』『石山軍艦』『本願寺大秘録』等々数えあげればキリがないほど異本が多い。私は参戦した僧侶の数だけあっても不思議ではないと考えている。
こうした軍記説教から芸能化した軍談(すなわち講談の祖)が生まれてくるのは不思議ではない。聖覚が生きた十二世紀末を経て十三世紀末には、ぼちぼちと芸能化した説教に対する批判の文章が現れてくる。虎関師錬(一二七八~一三四六年)は、著書『元享釈書』の中で、説教をこう批判している。
「変態百出し、身首を揺るがし音韻を婉く・・・・・流れて詐為俳優の伎となる」
変わった説教僧が次々と出て、身体をゆすり節をつけ、芸人と同じようになったと嘆いている。『沙石集』も同時代の本であるが、これも説教のテキスト集と考えた方が自然で、布施物(ギャラ)を貰っている三井寺の法師民部阿闍梨(あじやり)の話が出ている。プロ化した説教僧が出現しており、僧侶の格好だけした者まで登場してくる。僧籍を持たない者が軍記説教をしだしたとなると、講談師の祖型が出現したことになる。
足利義満の頃(一三六八~一三九四年)
「古山珠阿弥の弟子足利義満の前にて『大塔軍記』を読む。弁舌巧みで師匠をしのぐ物読み法師」(鹿苑院殿 厳島(いつくしま)詣記)
応永二三年(一四一六年)六月二八日
「物語僧『山名奥州謀反之事』を読む。」(看聞御記)
物語僧、物読み法師とはどういう存在なのか。桑田忠親は『大名とお伽衆』の中で、次のような見解を示している。
「物読み法師とは、貴顕の御前で、物語を朗読することを職掌としている僧体の者をいう。一名物語僧とも言ったようであるが、両者は必ずしも同一とは言えない。物読み法師と物語僧との差違であるが、純粋の僧でない僧体の物読み専門芸人の事を物読み法師と呼び、本職の僧侶であって余技に物読みをしているものを、物語僧と称したのではなかろうか」
物読み法師の出現と軍記説教とが合わせれば、軍談読み即ち講談師の出現間近といってよい。
江見河原入道と赤松法印
南陵は『続々明治期大阪の演芸速記本基礎研究』(大阪芸術大学博士論文、京坂(阪)における講談の歴史的検証とその周辺改題、たる出版)において、赤松法印講談の祖説を否定した。赤松法印説の根拠は次の記述によっている。多くの講談本に引用されているのが、関根黙庵の『講談落語の今昔譚』からの引用であり、逆のぼると黙庵の父の著書『只誠埃録』からである。そこには
「抑軍書講談の始ハ、赤松法印といへる者慶長の頃東照宮の御前に於いて源平盛衰記の講釈を度々言上せり、続いて諸侯に召され軍書を講じたれバ世人太平記読みと謂へり云々・・・・・続々武家閑談卷十一に見へり」
とある。よく似た記述が幕末の『我衣』にもある。
しかし、東照宮という表現は、家康没後三十年たって東照社に贈られた宮号であり、同時代の記述からの引用でないことを示している。『続々武家閑談』という本は、国書総目録にもない本である。「度々」という表現に注目しても、家康の日記類に太平記を聞いたという記述はどこにもない。『駿府記』『本光國師日記』『ト斎記』等々どこにもない。
すなわち、何の根拠もないのが赤松法印説なのである。
南陵が注目したのは、赤松法印よりおよそ一五〇年も前に存在した江見河原入道である。彼もまた太平記の研究家加美宏によって、赤松一族の江見河原氏の出身であることはわかっている。
赤松一族と説教の関係は説教僧で説教の名人赤松明秀(一四〇三~一四八七年)に始まると関山和夫の報告にある。赤松一族は自分の先祖の赤松一族が活躍する『太平記』を好んで説教の題材に選んだことだろう。
「江見河原入道為慰客寂読太平記也」(蔭涼軒日録)
物読み法師、江見河原入道が客の寂しさを慰めるために太平記を読んだのだ。しかも同じ蔭涼軒日録に
「江見河原の癖、好んで人の風度また言語を学ぶ。それ世の所謂狂言と云ふ者か」とある。太平記を芝居がかって読んだことから見て、記録上はっきりとした娯楽の太平記読みとみてよい。
私は今まで混同されてきたのが、「太平記読み」という言葉ではないかと考えている。兵法軍学の書として真面目に、講釈する太平記読みと娯楽として現代にもつながる太平記読みである。仮に赤松法印が家康の前で太平記を読んだとしても、軍学の講釈ではなかったか。二種類の太平記読みがあったとした方が、太平記読みの歴史がすっきりする。
落語の祖とされているのが、安楽庵策伝であり、これも説教僧であった。(一五五四~一六四二年)。小噺集である『醒睡笑』を著した。露の五郎兵衛(一六四三~一七〇三年)も露休という僧形でも辻談義もしたことが知られている。落語に関しては『国文学 解釈と鑑賞863』(平成15年4月号、舌耕芸落語誕生 至文堂)が軽便かつ要領を得ているので、参照されたい。